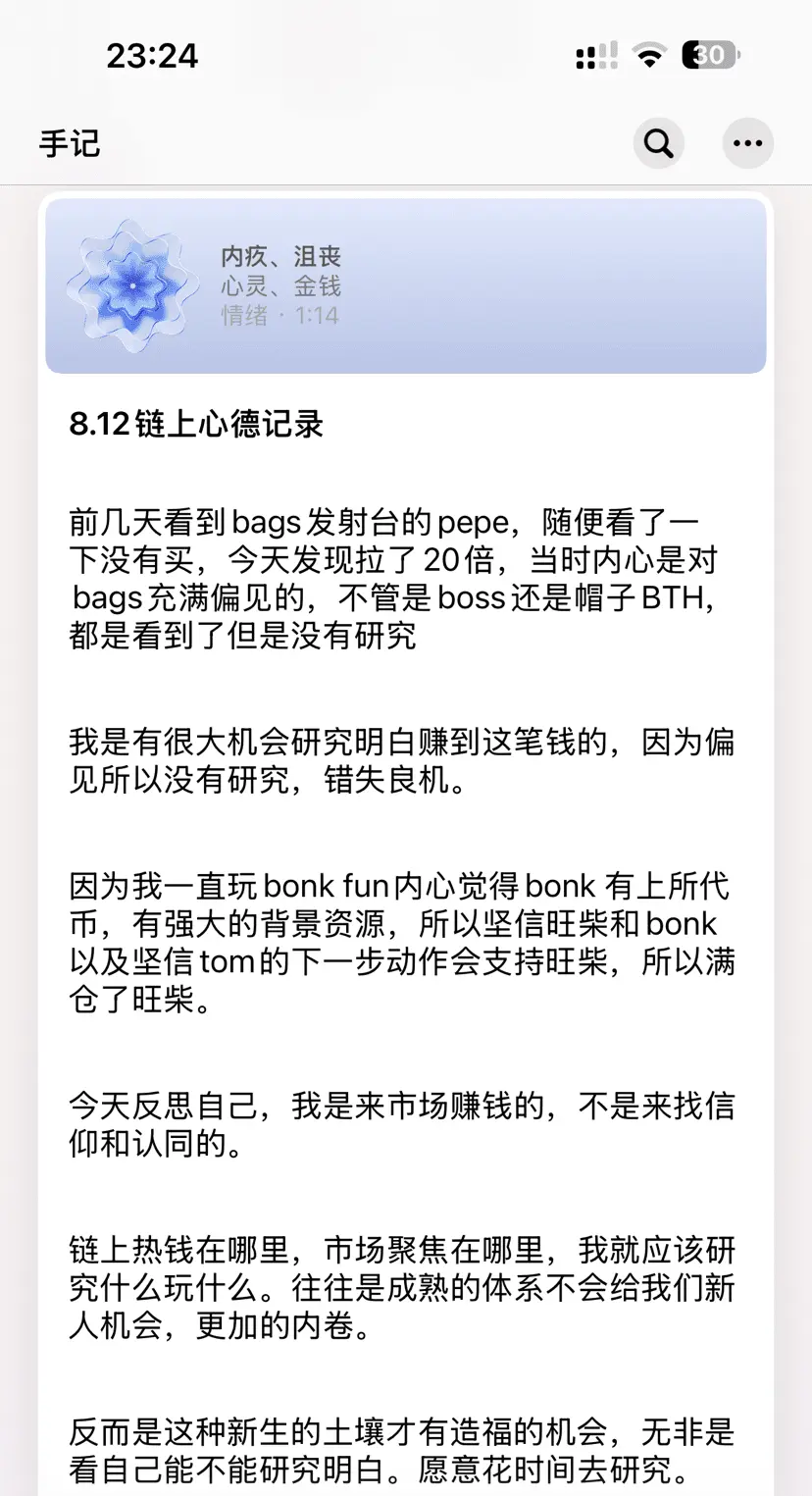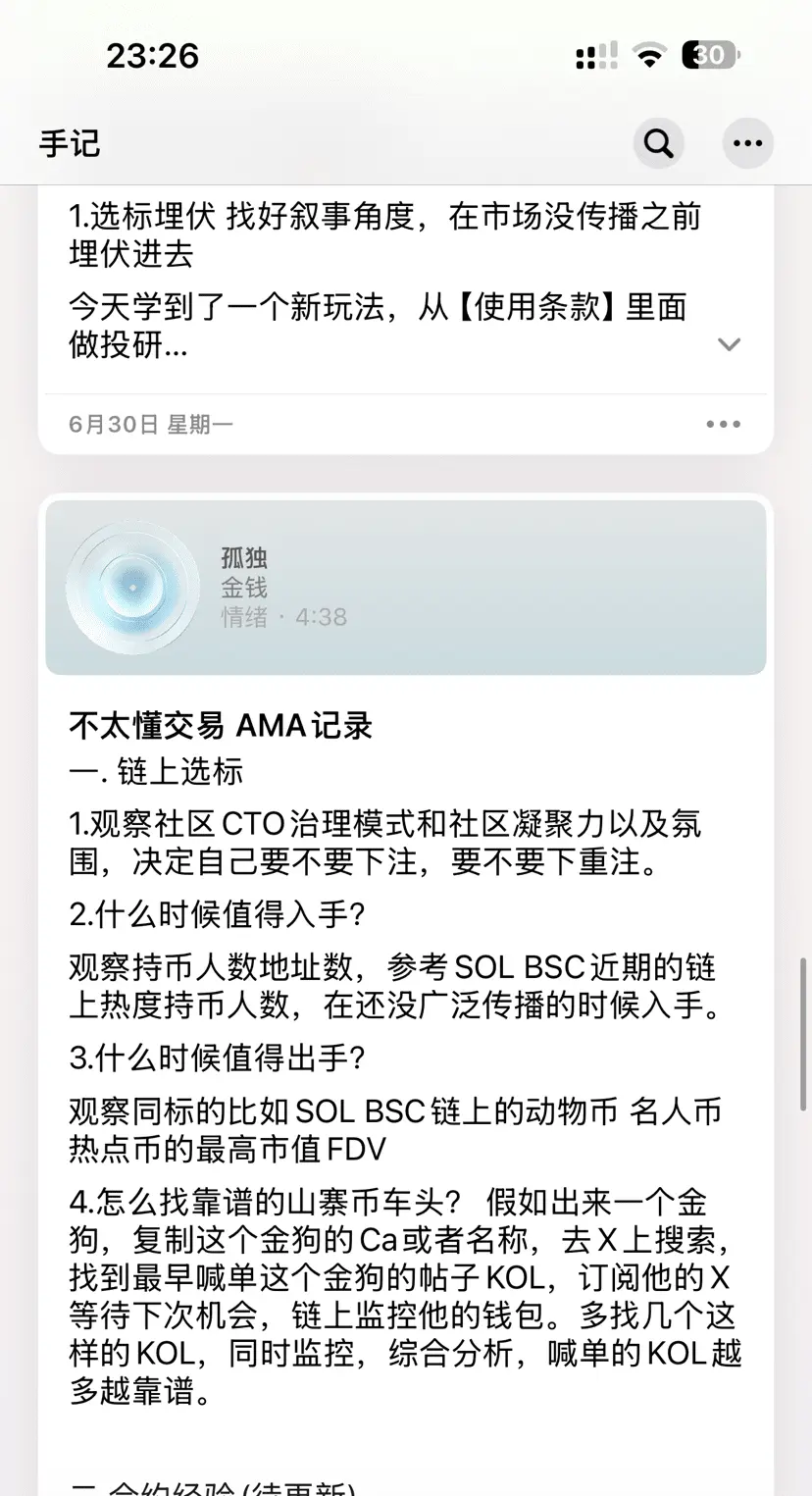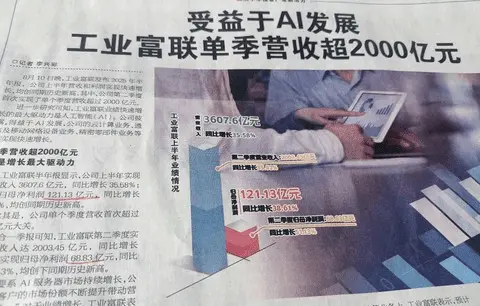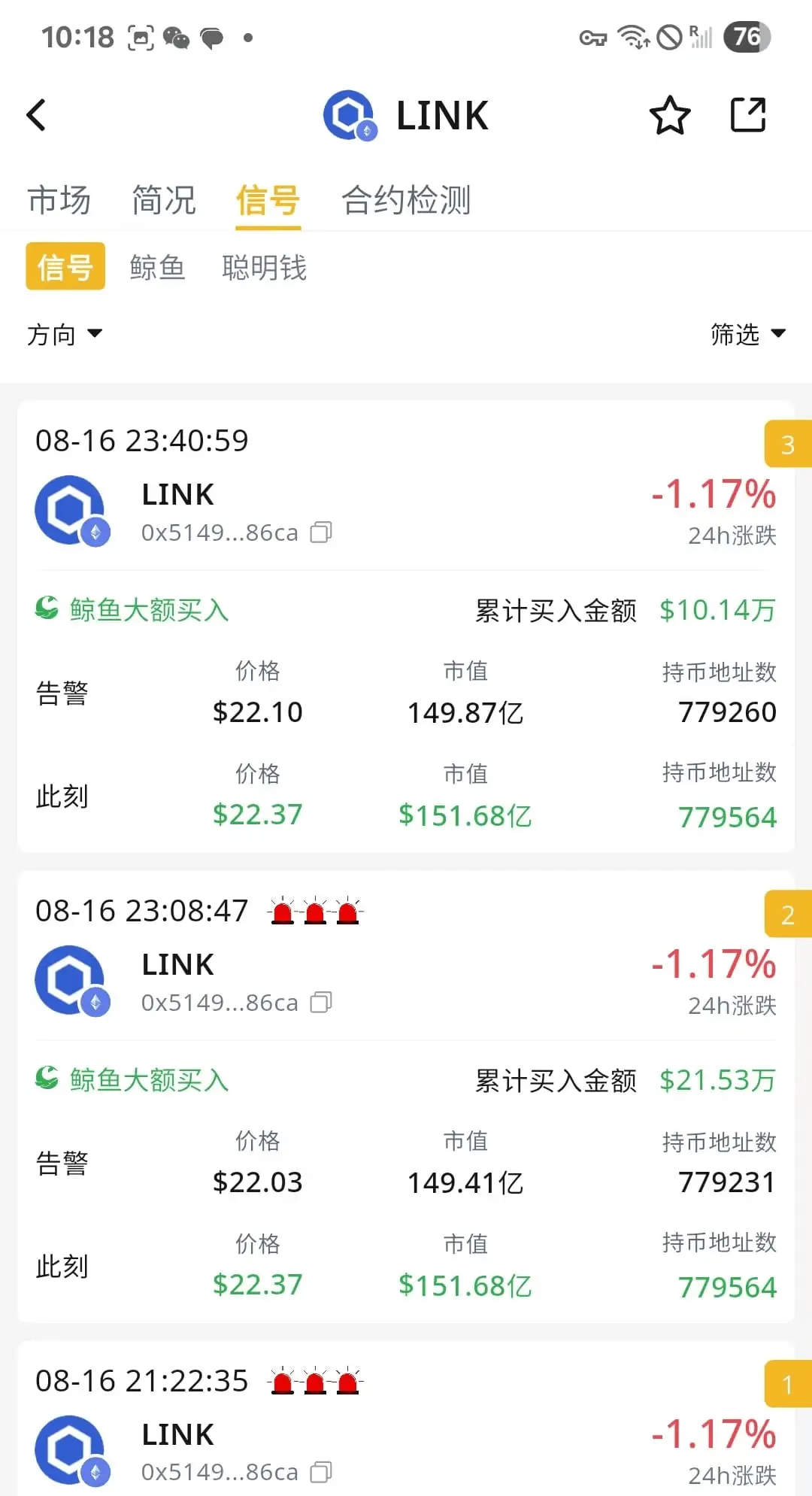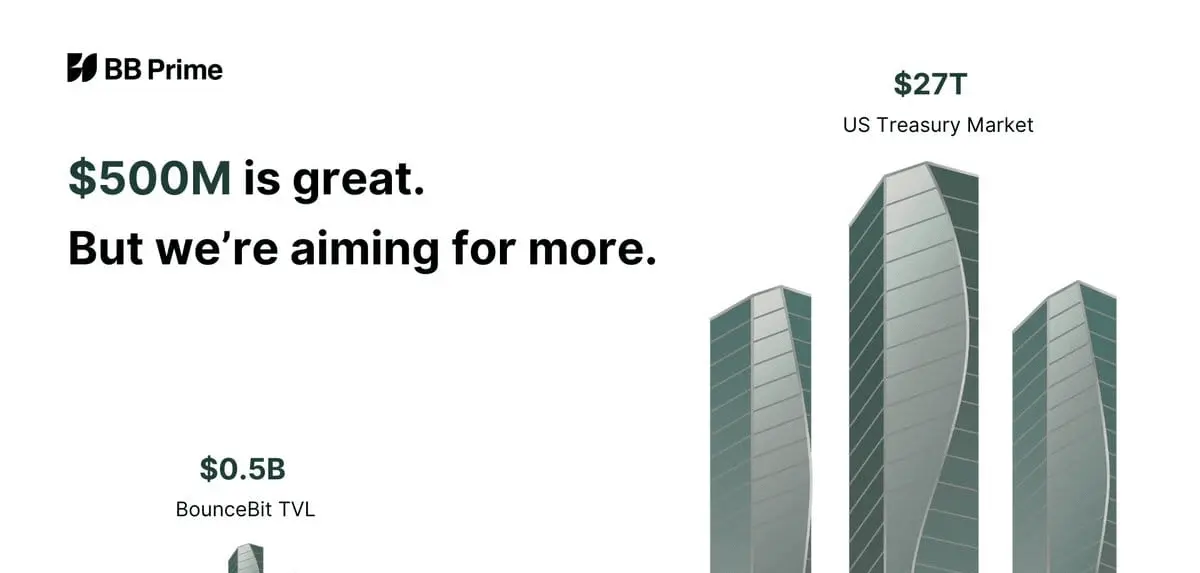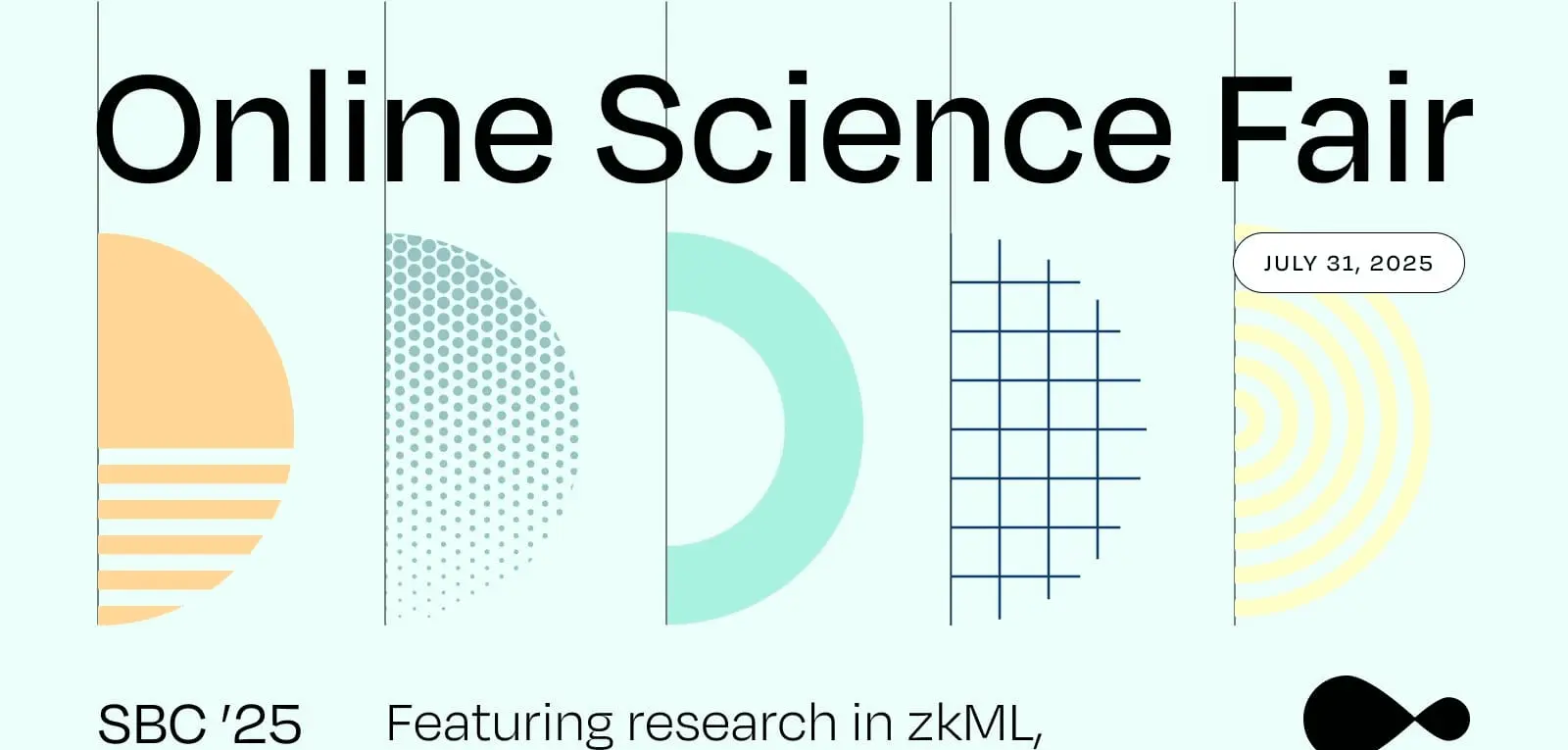最近、デジタルコレクションに関わる詐欺事件が業界内で広く議論を呼んでいます。2名の関与者はデジタルコレクションを利用して資金調達詐欺を行ったため、裁判所から8年半の実刑判決を受けました。この判決は業界内で大きな反響を呼び起こし、詐欺師を厳しく罰することを支持する声もあれば、業界全体の発展に影響を与える可能性を懸念する声もあります。
事件の詳細によれば、2023年にこの2人の被告は2888元の価格でAI生成の電子画像のバッチを購入し、第三者企業を通じてブロックチェーンに登録し、いわゆる「高価値デジタルコレクション」としてパッケージ化しました。彼らは「半額保証」や「必ず価値が上がる」といった宣伝手法を採用し、「ブラインドボックス」や「合成」といったマーケティング戦略で購入者を引きつけました。さらに、彼らは自分たちで売買を行うことで価格を人為的に引き上げ、購入者が返金を求めると直接ブロックする対応をしました。
しかし、この事件は一部の論争を引き起こしました。AI生成の画像が本当に価値がないのか疑問を呈する人もおり、これがデザイナーがコンピュータを使って創作する合法性に影響を与える可能性があると考えています。また、ブロックチェーン技術の価値に疑問を持つ人もおり、これが正当な事業を行っているデジタルコレクションプラットフォームに影響を与える可能性を懸念しています。
現在注目すべきは、市場に存
原文表示事件の詳細によれば、2023年にこの2人の被告は2888元の価格でAI生成の電子画像のバッチを購入し、第三者企業を通じてブロックチェーンに登録し、いわゆる「高価値デジタルコレクション」としてパッケージ化しました。彼らは「半額保証」や「必ず価値が上がる」といった宣伝手法を採用し、「ブラインドボックス」や「合成」といったマーケティング戦略で購入者を引きつけました。さらに、彼らは自分たちで売買を行うことで価格を人為的に引き上げ、購入者が返金を求めると直接ブロックする対応をしました。
しかし、この事件は一部の論争を引き起こしました。AI生成の画像が本当に価値がないのか疑問を呈する人もおり、これがデザイナーがコンピュータを使って創作する合法性に影響を与える可能性があると考えています。また、ブロックチェーン技術の価値に疑問を持つ人もおり、これが正当な事業を行っているデジタルコレクションプラットフォームに影響を与える可能性を懸念しています。
現在注目すべきは、市場に存